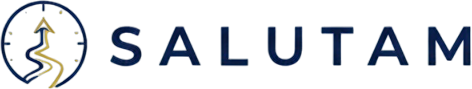中小企業のWeb担当者がやるべきことを徹底解説|これで迷わない

Web担当者に任命されたけど何をすればいいの?
やることが多くて何から手をつければいいかわからない!
Web担当者がどんな仕事をしているのか知りたい!
会社のWeb担当者のになったけど、何をしていいのかわからず悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
中小企業では、突然Web担当者になってしまうことも多いです。
理由も「若くてパソコンに詳しいから!」など、めちゃくちゃなことも多いので困りますよね。
ただ、Web担当者の仕事は幅広く、覚えることも多いです。
まずは、Web担当者が一般的にどのような仕事をしているのか、全体像を捉えておくと、やるべきことが明確になります。
そこで、今回は中小企業のWeb担当者がどのような仕事をしているのかを、わかりやすく解説していきます。
Web担当者になって何をしていいかわからず悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
Web担当者のやるべきことは多い!

Web担当者は、仕事の幅広く覚えることが非常に多いです。
一般的なWeb担当者がやるべきことは、11個あります。
- ホームページの目的を明確にする
- ホームページの目標設定
- ホームページの分析
- ホームページの改善と更新
- コンテンツの追加
- SNSの運用
- 広告の運用
- レポートの作成
- セキュリティ対策
- 各種アカウントの管理
- ホームページを死守する
規模や会社によってやるべきことは変わりますが、筆者がWeb担当者をしているときは上記をすべて行っていました。
では、ひとつずつ詳しく解説していきます。
ホームページの目的を明確にする

Web担当者になったら、最初に確認したいのがホームページの目的です。
ホームページの目的が具体的にわかっていないと、今後改善していくことができません。
- 商品を売りたい
- お問い合わせを増やしたい
- 申し込みを増やしたい
- 求人をしたい
- ブランディングをしたい
このようにホームページには目的があります。
ホームページに訪れたいユーザーに、何をしてほしいのかが明確になっていれば、成果も出やすく運用もしやすいです。
目的は1つに絞る
目的は1つに絞ることがオススメです。
というのも、いくつもの目的があるホームページは内容がわかりづらくなり、訪れたユーザーが何をしていいかわからなくなってしまいます。
その結果、どの目的も達成できなくなってしまいます。
「申し込みも増やしたい!」「求人もしたい!」など、複数の目的がある場合は、ホームページを分けてそれぞれ運用したほうが結果が出やすいです。
目的の優先順位を決める
ホームページを新規で制作できない場合は、目的の優先順位を確認しておきましょう。
1つのホームページに、目的がいくつもある場合は、優先順位をつけておけば運用する際も迷いません。
例えば、申し込みがもっとも重要な目的なら、求人のページなどは1ページ程度に抑えて、あくまでも副要素として扱います。
間違ってもトップページの目立つ場所に、求人バナーなどを表示させないようにしましょう。
訪れたユーザーに、求人をメインにしているホームページだと勘違いされてしまう可能性があります。
ホームページの目標設定

ホームページの目的を明確にしたら、具体的な目標を設定していきます。
目標を設定をすることで、ホームページの分析ができるようになります。
目標の例
- 問い合わせを月に100件獲得する
- 申し込みを月に100件獲得する
- メールアドレスを月に300件獲得する
- ホームページ経由で月に5人採用する
ホームページの目標は、具体的な数字を設定するようにしましょう。
「ブランディングをしたい」「アクセス数を増やしたい」などの目標を設定してしまうと、達成したかどうか判断できません。
目標を達成するための目標を設定
目標を設定したら、その目標を達成するための目標を設定していきましょう!
手前の目標を設定することで、やるべきことがより明確になります。
例えば、月100件申し込みを獲得することを最終目標に設定したとします。
現状で月に1,000人のユーザーが訪れていて、50件の申し込みがある場合は、月に2,000人訪れてくれれば目標を達成可能です。
また、申し込み率が0.5%で50件の申し込みがある場合は、1%にすることでも100件の目標が達成できます。
最終目標に対して、何をすれば達成できるのかを分析し、手前の目標を設定していきましょう。
手前の目標を決めるために、ホームページを分析していく必要があります。
ホームページの分析

手前の目標を決めるために、現状のホームページがどのような状態なのか把握する必要があります。
ホームページの分析に使うのは主に2つのツールを使います。
- Google Analytics
- Google Search Console
この2つを使うことで、現状のホームページの状態を分析できます。
ホームページを運用する場合、2つとも必須のツールになるので必ず導入するようにしてください。
Google Analytics
Google Analyticsは、ホームページを様々な数値で把握できる無料のツールです。
- アクセス数
- 申し込み率
- どこからアクセスがあったのか?
- アクセスしたユーザーがどれだけホームページに滞在したか?
上記以外にも様々なデータを調べられますが、まずはアクセス数・申し込み率を確認しておきましょう。
最初は何を見ればいいかわかりずらいですが、毎日見るようにすれば徐々に慣れていきます。
Google Search Console
Google Search Consoleは、どのようなキーワードでホームページが検索結果に表示されているのかを調べられる無料のツールです。
ホームページにエラーが出ている場合も、Google Search Consoleを見ることで確認できます。
Googleからどのような評価を得ているのかがわかるので、必ず導入するようにしましょう。
ホームページの改善と更新

ホームページの改善と更新は、主に2つを軸にして進めていきます。
- アクセスを増やす
- 問い合わせ・申し込み率を高くする
基本的にはこの2つを意識してホームページを運用していきます。
改善を繰り返して伸び悩んだ場合は、より詳しく分析をしていきますが、まずはこの2つだけに意識して運用をしていきましょう。
アクセスを増やす
ホームページにアクセスを増やすために、改善を繰り返していきます。
アクセスを増やすために行うことは3つです。
- コンテンツの質を高める
- 質の高いブログを書く
- SNSの運用をする
①、②、③の優先順位になります。
コンテンツの質を高める
コンテンツの質を高める改善を繰り返しましょう。
具体的には、以下のような改善を繰り返します。
- 訪れたユーザーにより詳しい情報を掲載する
- Q&Aページを追加する
- 過去の事例などのページを追加する
- 会社概要にアクセスマップや社長の写真などを追加する
- 古い情報は最新の情報に更新する
このような改善をしていくことで、訪れたユーザーがより念入りにホームページを見てくれるようになります。
そうすると、Googleからの評価も高くなり検索結果の上位に表示される可能性が高くなります。
重要なのは、ユーザー目線でコンテンツの改善を進めていくこと。
訪れたユーザーが疑問に思うことが無いように、コンテンツを作っていきましょう!
質の高いブログを書く
質の高いブログを書くことで、アクセス数を大幅に増やすことが可能です。
質の高いブログが書ければ、検索結果の上位に表示されるのでブログ経由でアクセス数を増やせます。
例えば、「ホームページ 制作会社 選び方」というキーワードで検索しているユーザーに、「ホームページ 制作会社 選び方」について詳しく書いたブログを書けばアクセスを増やせます。
「ホームページ 制作会社 選び方」でブログを書くときに重要なのは、「ホームページ 制作会社 選び方」で検索をしているユーザーの悩みを100%解決できるブログを書くことです。
ブログを書くときは、必ずユーザー目線で書くようにしましょう。
SNSの運用をする
余裕があるときは、SNSの運用も行いましょう。
SNSの運用は、ただ情報を発信するのではなく、ユーザーとのコミュニケーションを取るようにしてください。
そうすることで、フォロワーが増え告知したときなどに拡散されやすくなります。
ただし、SNSは一時的なアクセスは増えやすいですが、安定したアクセスは見込めません。
「コンテンツの質を高める」「質の高いブログを書く」の2つに時間を使って、余裕があるときにSNSの運用をするのがオススメです。
SNSを運用するときは、1日に1~3つ投稿するなど決めておくといいでしょう。
問い合わせ・申し込み率を高くする
問い合わせ、申し込み率を高くする改善を行っていきます。
改善ができると、問い合わせ件数、申し込み件数が大幅に増えるので常に意識しておきましょう。
具体的には、以下のような改善を繰り返します。
- 申し込みフォームを改善する
- 申し込みまでの動線を見直す
- ホームページの構成を見直す
問い合わせ、申し込み率の改善は、効果があったかどうかGoogle Analyticsで確認しながら修正を繰り返していきます。
申し込みフォームを改善する
申し込みフォームを改善することで、問い合わせ、申し込み率の改善が可能です。
申し込みフォームが複雑で、申し込みしにくくなっていないか確認してみましょう。
できるだけ、シンプルでわかりやすい申し込みフォームにすることが重要です。
申し込みまでの動線を見直す
申し込みまでの動線を見直すことで、問い合わせ、申し込み率を改善することが可能です。
どこから申し込みをすればいいかわからないホームページは、申し込み率が低くなってしまいます。
理想は常にページのどこかに、申し込みページに行けるボタンやバナーを設置しておくことです。
申し込みボタンが多くてダサいと思うかも知れませんが、しつこいぐらいがいいです。
ホームページの構成を見直す
ホームページの構成を見直すことで、問い合わせ、申し込み率を改善することが可能です。
ページの構成は、ユーザーが知りたい情報を上部に持ってくるようにしましょう。
ページ上部に、いきなりスタッフ紹介などのコンテンツがあったらすぐに離脱されてしまいます。
(※スタッフについて知りたいユーザーを集めている場合はOK)
ホームページに訪れたユーザーは「何を知りたいのか?」「どのような目的で訪れているのか?」を常に考えて、構成を考えていきます。
コンテンツの追加

Web担当者は、日々様々なコンテンツを追加していきます。
前述したアクセスを集めるためにコンテンツを追加する以外にも、他部署から新しい情報をもらい、コンテンツを追加することも多いです。
ページを追加する
新しい事業がスタートしたり、新しいサービスが始まったときは、新規でページを制作します。
必要な画像や文章などの素材を集めて、ユーザーにわかりやすいようにページを制作しましょう。
他部署から依頼された場合は、ページを作る目的を明確にし、他のページと整合性が取れるようにします。
新着情報の追加
会社の新着情報の追加依頼も頻繁にきます。
具体的には、夏季休暇の情報だったり、会社の事業についての内容だったりします。
ブログとは違うので、ユーザーにわかりやすいように、シンプルに掲載するようにしましょう。
メルマガを送る
メルマガを発行している会社もあります。
メルマガの発行はWeb担当者の仕事になることがあるので、確認しておくといいでしょう。
会社からの新着情報を、メルマガで受け取っているユーザーは意外に多いので効果は高いです。
筆者もいくつかメルマガを受け取っています。
SNSの運用

会社のSNSをWeb担当者が運用することも多いです。
Web担当者になったら、現在運用されているSNSは把握しておくようにしましょう。
会社によっては、部署ごとにSNSを運用していたり、放置されたSNSがあったりと収集がつかなくなっていることも多いので注意が必要です。
また、SNSを運用する場合、どのような目的で開設されたSNSなのかをしっかりと把握しておくことも大切です。
広告の運用

Web担当者がWeb広告の運用をすることも多いです。
実際に、Web担当者が広告を運用せずに外注をしている場合は、打ち合わせに参加してどれだけ広告の効果が出ているか確認する必要があります。
専門用語が飛び交うことが多いので、最低限の専門用語は理解しておかなければいけません。
もし、わからないところがある場合は、素直にわからないことを伝え、詳しく説明してもらうようにしましょう。
レポートの作成

Web担当者は、上司や社内に向けてレポートを作成し提出します。
筆者の場合、ホームページのアクセス数・問い合わせ数・申込数などを1週間に1度提出していました。
また、違う情報が欲しいと言われたときは、レポートに新しく項目を追加することもあります。
レポートを見る人は、Webに詳しくない人もいるので、できるだけわかりやすく作成することが重要です。
セキュリティ対策

ホームページのセキュリティ対策もWeb担当者の仕事です。
大手のホームページだけではなく、中小企業のホームページも狙われることは多いです。
実際に、筆者が以前に働いていた制作会社では、ウィルスを埋め込まれて大変なことになった経験があります。
ウィルス対策ソフトの導入、定期的なパスワードの変更、使用されいないユーザーの削除など、基本的なことを定期的に行うようにしましょう。
各種アカウントの管理

Web担当者は、各種アカウントを管理します。
ホームページにログインできる人の管理、SNSの各種アカウントの管理など、会社でどのような人がアクセスしているのか管理するようにしてください。
管理しておけば、他部署からアカウント情報を聞かれたときも対応できます。
恐いのが勝手にアカウントを作られて、知らないところで運用されるとホームページの内容が変わっていたり、不要な情報が追加されていたりするリスクがあります。
Web担当者になったら、あらかじめどのような運用になっているのか、細かく確認しておくといいでしょう。
ホームページを死守する

ホームページを死守するのはWeb担当者の重要な仕事です。
Web担当者になると、様々な人から情報を掲載して欲しいと依頼がきます。
言われたまま、なんでもかんでも掲載してしまうと、当初確認したホームページの目的からどんどんズレていってしまいます。
ホームページの目的からズレた掲載依頼については、きっぱりと断ること勇気も必要です。
断る際は、代替案を出してあげれば納得してくれることがほとんどです。
中小企業のWeb担当者がする仕事の優先順位

Web担当者は、ホームページの目的を達成できる仕事をできるだけ優先するようにしましょう。
他部署からの修正依頼に追われていたら、ホームページの改善もできなくなってしまいます。
(※情報を最新にする必要があるので、依頼内容によっては急ぎになることもあります。)
Web担当者になると様々な仕事が舞い込んできます。
忙しくなると、何を優先していいのかわからなくなってしまうので、何を優先するのか整理してから仕事に取り掛かるようにするといいでしょう。
外注も検討する

業務が多い場合は、外注を利用するのもオススメです。
ホームページの運営では、バナー制作、コーディング、記事の制作、広告の運用などは外注できます。
あなたはホームページの方向性と今後の戦略に注力して、実際の作業は外注したほうが効率的です。
フリーランスに依頼する
バナー制作、コーディング、記事の執筆などは、フリーランスで仕事を受けている人がたくさんいます。
クラウドソーシングサービスで見つけられるので、一度確認してみるといいでしょう。
人によってスキルにばらつきがあるので、実績などを見て選ぶようにしてください。
広告代理店を利用する
もし、広告の運用に詳しくない場合は、広告代理店の利用がオススメです。
Web広告には、Google広告、SNS広告(X、Facebook、Instagram、TikTok…)など、様々な媒体があります。
それぞれの広告に特徴があるので、広告の運用は専門家に任せたほうが効率的です。
中小企業を対象にしている広告代理店を利用すれば、低予算でもWeb広告を運用することが可能です。
私達(SALUTAM)でも低予算で広告の運用をしていますので、広告の運用を検討している方はご検討ください!

中小企業のWeb担当者が最低限覚えたい用語

Web担当者になったら、最低限の専門用語は覚えるようにしましょう。
よく使われる用語は、下記になります。
- CV(コンバージョン)
-
CV(コンバージョン)は、Webサイトで「目標」を達成することを言う。
例えば、商品を買ってもらったり、メールを登録してもらうこと。
- CVR(コンバージョン率)
-
CVR(コンバージョン率)は、たくさんの人がWebサイトを見て、どれくらいの人が目標を達成したかの割合。
例えば、100人がサイトを見て、10人が買い物をしたら、CVRは10%になる。
- SEO対策
-
SEO対策は、Webサイトを検索で上に表示させることを言う。
例えば、グーグルで「おいしいケーキ」と検索したときに、ケーキ屋さんのサイトが上に出るようにすること。
- PV(表示回数)
-
PV(表示回数)は、Webページがどれくらい見られたかを数えること。
例えば、この記事が100回表示されたら、100PVになる。
- セッション
-
セッションは、1回の訪問のこと。
例えば、あなたがサイトを開いてから閉じるまでが1セッション。
何回も訪問すると、それぞれが別のセッションになる。
他にも様々な用語がありますが、その都度わからない用語は調べるようにしましょう。
また、打ち合わせでわからない用語があったら、遠慮なく聞くようにしてください。
大抵は親切に教えてくれます。
中小企業のWeb担当者にオススメの書籍
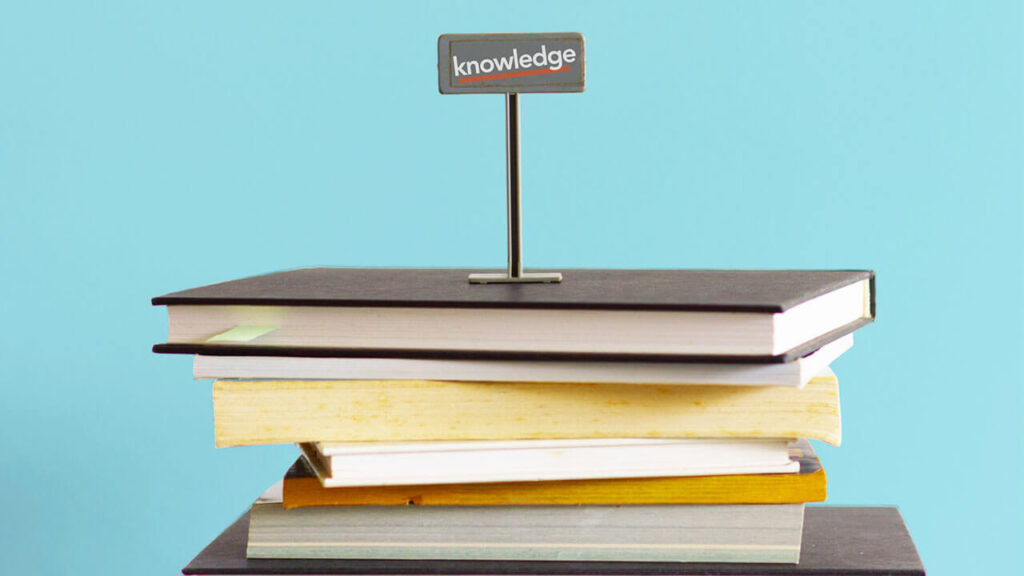
Web担当者になったら、本で仕事の流れを覚えるのもオススメです。
筆者も中小企業のWeb担当者になったときは、本で知識を蓄えました。
ある程度、専門用語や仕事の流れがわかってくれば、Googleで検索すれば大抵のことはわかるようになります。
まずは数冊本を読んでみましょう。
Web担当者の仕事は理解されにくい

中小企業のWeb担当者は、孤独になことが多いです。
「パソコンを触っているだけで、何をしているかわからない。」
「座っているだけで楽そう」
「成果が上がったのは現場が頑張ったからだ!」
日々改善と修正を繰り返しても、他の人にはあまり伝わりません…。
心が折れそうになることもありますが、無視して黙々と仕事をしましょう。
そして、しっかりとレポートを作成して、どのように数字が変わっているのか社内で共有させることも大切です。
まとめ
この記事では中小企業で働く一般的なWeb担当者の仕事を紹介しました。
まとめると下記になります。
- ホームページの目的を明確にする
- ホームページの目標設定
- ホームページの分析
- ホームページの改善と更新
- コンテンツの追加
- SNSの運用
- 広告の運用
- レポートの作成
- セキュリティ対策
- 各種アカウントの管理
- ホームページを死守する
中小企業のWeb担当者の仕事は幅広いです。
すべてひとりで行うのは限界があるので、作業などは外注して効率化することも重要です。
弊社では中小企業のWeb業務をサポートしています。
サポートが必要になったら思い出していただけると幸いです!